酪農の担い手問題
 北海道新規就農酪農・畜産クラスター協議会
北海道新規就農酪農・畜産クラスター協議会
農場リース事業の補助額を大幅拡充
農場リース事業の支援内容が平成27年度から拡充された。初妊牛や作業機械のリース補助率が拡大し、新規就農者の負担軽減につながっている。生産基盤の維持・強化に向けて、道内各地の担い手確保に弾みをつけることに期待がかかる。
酪農基盤の維持・強化を図るためには、既存農家の規模拡大もさることながら、いかにして新規就農者を確保するかが大きな課題だ。
ただ、酪農は初期投資額が1億円を上回ることも珍しくなく、就農希望者にとって資金面でのハードルは極めて高いのが実情だ。特にここ1~2年は、全国的な乳牛頭数の減少で初妊牛価格が異次元の高値へと暴騰しており、新規就農者にかかる負担は一層重いものとなっている。
ホクレンによると、10月19日に開かれた十勝乳牛市場の初妊牛平均取引価格は86万1879円。前回・10月5日比8.5%(6万7549円)高、前年比36.1%(22万8630円)高と跳ね上がり、全道の過去最高値を更新している。
表1 ホクレン乳牛市場の初妊牛平均取引価格
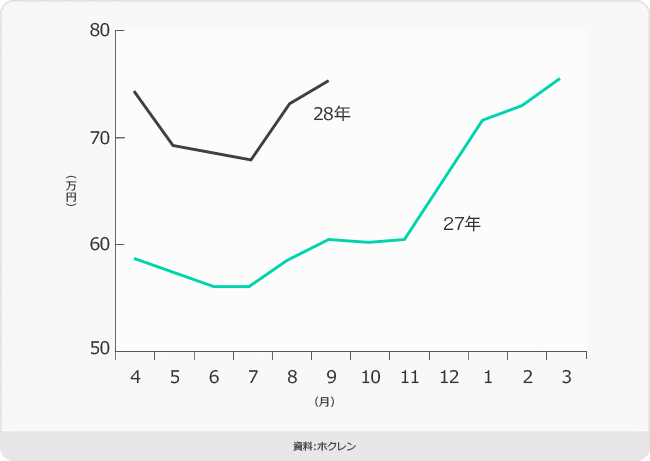
仮に、新規就農者が市場から初妊牛を40頭導入したら、費用は合計3447万5160円にも及び、1年前に就農した場合に比べ、900万円以上も負担が大きくなる計算だ。
北海道の乳牛市場が暴騰しているのは、F1(交雑種)種付け率の上昇で全国的に乳牛頭数が減少していることに加え、畜産クラスター関連事業を活用した規模拡大で、初妊牛への引き合いが強まっていることが背景にある。
相場は今後、春産みが出回るにつれて、さらに値上がりするとの見方が強い。酪農に関心がある人たちが少しでも新規参入しやすい体制を整えるためにも、就農希望者の金銭的負担を軽減するための支援策が一段と重要性を増している。
初妊牛導入への支援が拡充
こうした初妊牛相場の高騰で新規就農者を取り巻く環境が厳しさを増す中、北海道農業公社の農場リース事業の支援内容が平成27年度から拡充・強化された。
農場リース事業は、北海道農業公社が離農跡地や後継者不在の施設を一括して取得・補改修し、初妊牛を導入した牧場を新規就農者に5年間貸し付けてから、売り渡す事業。
北海道畜産振興課によると、道内では昭和45年~平成26年までの44年間、酪農への新規参入は計604戸に及んだが、このうちの311戸(51%)が農場リース事業を活用した。平成26年も、新規参入16戸のうち、半数以上の9戸が農場リース事業を利用しており、道内定番の事業として多くの新規就農者を酪農現場に送り出している。
表2 北海道の酪農新規就農者数の推移

資料:北海道農政部
同事業の支援内容が拡充・強化されたのは、就農希望者の初期投資額を圧縮するのが目的。
財源が平成27年度に「強い農業づくり交付金」から「畜産クラスター関連事業」へと移管されたタイミングに合わせて、乳用牛導入にかかる補助金の上限を1頭当たり17万5000円から、最大27万5000円へと増額した。
また、作業機械などのリース補助率も従来の3分の1から2分の1となり、就農希望者の負担がより軽減される形となった。
表3 農場リース事業の概要
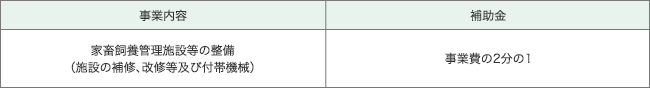
資料:北海道農業公社
酪農主産地の農協関係者は「相場が大幅に値上がりしているため、新規就農者が計画通りに初妊牛を買うことが難しくなっている。農場リース事業で初妊牛導入への支援が手厚くなったことは大きい」と評価している。
地域支援との併用で負担圧縮
農場リース事業を活用する就農参入者は、北海道農業公社と道、北海道酪農畜産協会らで構成される「北海道新規就農酪農・畜産クラスター協議会」の一員となり、新規就農に向けてクラスター計画を策定する。酪農経営の安定を図るため、新規就農から就農後の営農まで、包括的な支援を受けることが可能だ。
北海道では今年度、農場リース事業を活用し、前年度の9戸を上回る15戸が新規就農する予定。
協議会の構成員である北海道は「道内では、新規就農者の半分以上が農場リース事業を活用している。各市町村や農協が独自に取り組む就農支援などと組み合わせることで、より初期投資額を圧縮できるはずだ。酪農経営の安定を図るためにも、ぜひ有効活用してもらいたい」(畜産振興課)と強調する。
毎年200戸前後の酪農家が離農を選択する中、生産基盤の維持・強化に向けて、充実した担い手対策を講じる地域は多い。就農支援金や利子助成、固定資産税への補助のほか、農場リース事業を活用する酪農生産者に対し、賃借料の補助を行う市町村や農協も目立つ。こうした支援策を農場リース事業と併用すれば、新規就農者は金銭的負担を大幅に軽減することができる。
道畜産振興課は「日本の生乳生産の過半を占める北海道で、酪農の担い手対策は極めて重要。農場リース事業は支援内容が拡充され、新規就農者にとっては、より使いやすい形となった。生産基盤の維持・強化を図るためにも、道としては引き続き担い手確保を支援していきたい」と力を込めている。


